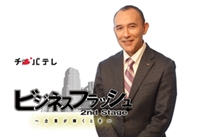パワハラ・セクハラなどのハラスメントは、職場に深刻な影響を与えます。
被害者対応を誤れば労災や損害賠償請求に発展し、加害者対応を誤れば「処分が甘い」「逆に人権侵害だ」と二次トラブルに発展しかねません。
本記事では、実際のセクハラケースをもとに、被害者・加害者・企業リスクの3つの観点から、社労士・弁護士の視点で整理しました。
1. 企業に迫る損害賠償リスク
ハラスメント事案で会社が負う可能性のある責任は大きく分けて2つです。
使用者責任(民法715条)
加害者の不法行為について、会社が損害賠償責任を負う可能性。
安全配慮義務違反(労働契約法5条等)
職場環境を守らなかったとして慰謝料を請求される可能性。
訴訟では、記録(発言・経緯・面談メモ等)の有無が勝敗を分けます。
記録保全・対応経過の文書化・弁護士対応の準備が不可欠です。
2. 労災・退職処理・社会保険の実務対応
ハラスメントによるメンタル不調では、労災給付や傷病手当金の利用が焦点になります。
労災かどうかを判断するのは労基署(会社は拒否できない)
傷病手当金は退職後も継続受給が可能
退職処理では以下がポイントです。
出勤率8割未満でも、会社の裁量で有給休暇を付与できる
退職日を延長(例:9月→10月)することも可能
有給消化で退職するのが基本、社会保険料清算は分割や相殺を柔軟に
説明不足や曖昧な処理は「有給の買い取りだ」「不当な精算だ」と誤解され、トラブルの火種となります。
3. 被害者対応の実務ポイント
被害者に不信感を抱かせないためには、次の点が重要です。
記録を残す:発言・面談を必ず書面化
不確実なことは言わない:「労災で上乗せがある」といった曖昧な発言は厳禁
正しい制度説明:離職票発行、失業給付と傷病手当金は同時受給できない等
会社の説明ミスが「誤案内による損害」として賠償請求されるリスクもあります。
4. 加害者への対応:懲戒処分と再発防止
ハラスメント事案では、加害者への対応も極めて重要です。
事実確認と聴取
被害者と加害者は別々に聴取
感情的判断は避け、客観的証拠を集める
書面で残すことで後の紛争防止につながる
懲戒処分の検討
就業規則に基づき「けん責・減給・出勤停止・諭旨解雇」などを選択
処分の公平性を担保するため、過去事例や処分基準を参照
再発防止策
ハラスメント研修の実施
管理職への指導・評価体制の強化
再発時はより重い処分を検討
加害者の人権配慮
吊し上げや過度な情報公開は逆効果
あくまで「規則と法令に基づく公正な処分」で対応すること
被害者保護と同時に、加害者への正当な手続きと処分が、社内外からの信頼維持に不可欠です。
5. 企業が今すぐ備えるべき鉄則
本事案から抽出できる鉄則は以下の3つです。
記録を残すこと
説明を順序立てて書面化すること
弁護士対応を想定しておくこと
そして、加害者への懲戒処分と再発防止策も「並行して」進める必要があります。
まとめ
ハラスメント事案は「被害者への対応」だけでも、「加害者への処分」だけでも不十分です。
労災・損害賠償・退職処理・社会保険精算まで、法的リスクが複雑に絡むため、全体像を見据えた対応が求められます。
企業が守るべきは、
被害者の信頼を守る配慮
加害者への公正な処分
会社としての法的リスク管理
この3つのバランスです。
不用意な一言や曖昧な処理が訴訟に直結することもあります。
社内体制を整え、専門家と連携することで、トラブルを未然に防ぎましょう。

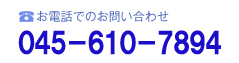













 助成金診断
助成金診断